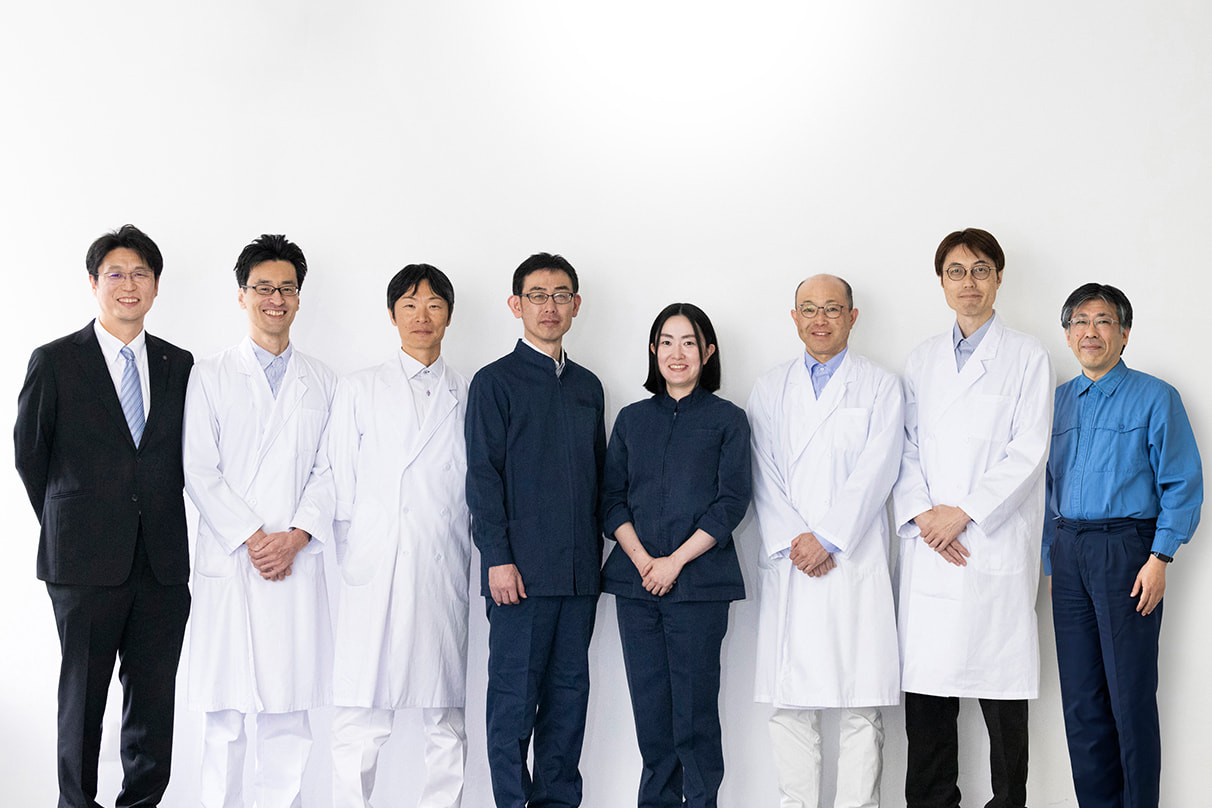プロジェクト
ストーリー
早く、細かく、分かりやすく—
医薬品の安全性情報を届けるための
システム刷新プロジェクト

医療関係者が求めている医薬品の副作用情報を、迅速かつ分かりやすく伝えるために。安全性情報部が主体となり、各部署からメンバーを集めて挑んだ情報提供システムの大規模刷新。
キッセイ薬品では、2006年に業界に先駆けて「安全性情報提供システム」を開発し、MR(医薬情報担当者)を通じて医療関係者への迅速な情報提供を行ってきました。その後10年以上が経ち、オンラインでのコミュニケーションが増加。求められる情報も変化してきました。情報をより分かりやすく届けたいという声が社内から上がってきたこともあり、安全性情報部がシステムの大規模刷新プロジェクトを立案。医療関係者が直接情報を検索できるシステム「KISSEI Safety LINK」の開発に、メンバー一丸となって取り組みました。
プロジェクトメンバー
左右にスライドしてご確認ください
時代に合った医薬品の安全性情報を届けるために
各関係者からの声を基に、システム刷新を決意
―まずは、プロジェクトの概要を教えてください。

I.T
私たちが所属する安全性情報部が主体となり、安全性情報提供システムの大規模刷新に取り組んだプロジェクトです。安全性情報部は、その名のとおり「医薬品の安全性に関する情報を扱う部署」。当社で販売している医薬品の副作用情報などを収集し、安全に使用してもらうための情報を発信しています。今回のプロジェクトも、情報発信業務の一環として取り組みました。

U.H
プロジェクトの目的は、医療関係者が「いつでも」「直接」「最新」の安全性情報に「簡単に」アクセスできるようにすることです。キッセイ薬品では2006年に安全性情報提供システムを開発し、MRを通じて医療関係者からの問い合わせに迅速に対応してきました。このシステムをさらに進化させようということで、今回のプロジェクトが始動したのです。

K.M
前身のシステムは業界に先駆けて開発したということもあり、当時は大きく注目されていました。ただ、長年使い続けているうちに「今の時代の技術を使えば、もっと便利になるのでは」という部分がいくつか出てきたのです。その一つが、情報を提供するまでのスピード。私自身、医薬営業本部に所属していた頃に前身のシステムを使うことが多かったのですが、時間がかかる点に若干のもどかしさを感じていました。医師から「この医薬品の副作用の」発現率ってどのぐらいなのでしょうか。どのような層の患者さんに多いのですか?」と聞かれた際に、どうしてもシステムの操作や読み込みに時間がかかってしまう。情報を提示した後の議論が大切なのに、そこまで辿り着けないということもありました。そのため、見たい時にすぐに情報を確認できるようにしたいとずっと思っていたのです。

A.M
分かります。私は以前、当社の医薬品に関するお問い合わせ対応を担う「くすり相談センター」という部署に所属していたため、前身のシステムをよく使用していたのですが、日頃から情報の見せ方を改善したいと思っていました。グラフ化したり色分けしたりできれば、より分かりやすく伝えられるのではないかと。そこで、誰が見ても重要なポイントが一目で分かるシステムに刷新できないかと考えていました。

U.H
安全性情報に対するニーズが変化してきたことも今回のプロジェクトに大きく関係していますよね。コロナ禍を経てオンラインでのコミュニケーションが増えたことで、MRが所持する端末だけでなく、医療関係者の手元の端末で情報を確認したいという声が届くようになりました。医療関係者が情報を直接見られるようになれば、先ほどK.Mさんが言っていたように「情報を提示した後の議論」に集中できるようになる。医療関係者にとっても当社にとってもポジティブな効果があるため、新システムの必須要件として「医療関係者が情報を直接確認できる」ことを組み込むことにしました。

A.M
そうですね。医療関係者が直接情報を確認できるようになれば、解決のスピードが上がり、当社の医薬品をより効果的に使っていただける。安全性情報部としての使命を果たすことにもつながりますね。

I.T
ニーズの変化という点では、キッセイ薬品が希少疾病の医薬品に注力するようになってきたことで、これまで以上に詳細かつ速やかな情報提供が求められるようにもなってきましたよね。こうした背景を踏まえ、操作性や視認性、アクセスのしやすさ、情報の詳細さを意識した新システム「KISSEI Safety LINK」開発プロジェクトがスタートしました。

各部署からプロジェクトメンバーを集め、
多様な視点を大切にしながらプロジェクトを進行
―本プロジェクトにおけるそれぞれの役割と、プロジェクトの進め方について教えてください。

I.T
まずはプロジェクトメンバーを集めるところから始めました。安全性情報部から私たち4名、そして医薬営業本部やくすり相談センター、広報部や法務部など、さまざまな部署から10名ほどに参加してもらいました。私はプロジェクト責任者として、上層部への提案などを担当しました。本プロジェクトの中心となって進行してくれたのはU.HさんとK.Mさんでしたね。他の業務もある中、本当によくやってくれたと思います。

U.H
ありがとうございます。私はプロジェクトリーダーとして、要件を整理してプロジェクトの方向性を決める他、システムの仕様やデザインの検討、開発会社とのやり取り、個人情報保護に関する検討などを推進する役割を担いました。

K.M
私は主に情報の交通整理を担当し、各担当者のタスク管理や、やり取りをするためのプラットフォームの整備、他部門との窓口対応などを担いました。多くの部署と連携して進めるプロジェクトだったため、認識の食い違いや情報がもつれないよう、常に注意して進めました。

A.M
私は、安全性情報を医学的な視点から評価するファーマコビジランスとして、内容の確認や、医療関係者が理解しやすいビジュアルの検討などを担当しました。

U.H
安全性情報と一口に言っても、副作用の種類や個々の患者さんの背景情報は多種多様であり、それらをどうまとめればよいかには医学的な視点が必要です。この領域はかなり高い専門性を求められるため、A.Mさんに非常に助けられました。こうした役割分担の下、前身のシステムと対比しつつ、どんな情報を取り扱うか、どのように表示するかなどの要件をまとめていきました。

I.T
前身のシステムを使って医療関係者とコミュニケーションを取っている部署や、社外への情報発信を取りまとめる部署など、このシステムに関わりがある部署のメンバーを集めたため、異なる視点からさまざまな要望が上がりましたよね。

U.H
医療の第一線に近い人だからこそ必要だと気付いた点もあるし、情報保護の面などから譲れない点もある。一部の意見を重視するのではなく、それぞれを尊重しながら進めていきました。どの意見にも意味があり、優先順位を付けてはならないと考えたのです。

K.M
今回のプロジェクトの核として、医療関係者が情報を直接確認できるシステムにするという要件は決まっていたため、意見が相反する際は「医療関係者にとってどうか」という視点で着地点を見つけていきました。特に、医療関係者と直接関わることの多い医薬営業本部からの情報収集には注力しましたね。


大きな壁を乗り越えられたのは、
皆が同じ想いを持っていたから
―プロジェクトを進める上で、特に難しかったのはどのような点でしたか?

U.H
「どこまで情報を開示するか」と「情報の有用性をどう担保するか」のバランスを取ることが一番のハードルでした。システムを使う側からすれば、当社が保有する全ての情報が見られるに越したことはありませんが、キッセイ薬品としては、個人情報の保護や情報流出のリスクを鑑みなければいけません。特に医療情報は、慎重に扱う必要があります。そのため、リスクを最小限にした上で、可能な限り有用な情報を提示することが求められました。この部分は、A.Mさん中心に情報を整理してもらいましたね。

K.M
リスクについてもう少し詳しく説明すると、例えば「合併症・原疾患」を検索して指定難病が含まれていた場合、指定難病は患者さんの数が少ないため簡単に個人が特定できてしまう可能性があります。ご本人の許可なしに、プライバシーに関わる情報を公開してしまうことになりかねません。そのため、症例の合併症の中に指定難病が含まれていた場合、病名を隠すなどマスキングのルールを設けました。社内のデータベースで管理している疾患名が、指定難病名と必ずしも合致するわけではなかったので、一つひとつ病態を照合する必要があり、かなり苦労しましたね。

I.T
もし誤って重大な情報を公開してしまえば、システムに対する信頼だけでなく、キッセイ薬品全体への信頼を揺るがしかねない。そのため、どの情報をどこまで公開するかの調整には非常に神経を使いました。

U.H
I.Tさんが言ったとおり、企業全体の信頼に関わるため、法務部との検討では厳しいフィードバックを多くもらいました。私たちとしては、医療関係者に少しでも多くの情報を届けたいという想いがあるものの、情報保護の面から看過できない部分もあるということで、何度も議論を重ねました。ただ、医療関係者の役に立ちたいという想いは全員に共通していたため、その想いを軸に建設的な議論ができたことが今回のプロジェクトの成功につながったと思います。皆が同じ想いを持っているかどうかは、チャレンジングな試みをする上で必須だと改めて痛感しました。

K.M
同感です。ここまで大規模なシステム刷新は初めてだったので、先ほど挙げた情報の開示範囲と有用性の担保のバランス以外にも、画面デザインの調整など苦労した点はいくつもあります。それでも一つひとつの壁を乗り越えることができたのは、医療関係者のため、ひいては患者さんのためという想いが前提にあったからだと思います。

I.T
結局、精神論かと思われるかもしれませんが、同じ方向を向いていることは大規模なプロジェクトを進める上で非常に大切です。「安全性情報提供システム」を開発した時から、医療関係者や患者さんのためという想いは変わっていません。そして私たちは、会社の代表としてその取り組みを成功させる使命がある。そんな想いで、このプロジェクトに向き合い続けました。

プロジェクトはここで終わりではない
より良いシステムへと進化させていく
ー最後に、今後の展望について教えてください。

U.H
「KISSEI Safety LINK」が完成した瞬間は、張り詰めていた緊張が解けて「ついにここまできた!」という達成感と充実感が一気に押し寄せました。最後まで駆け抜けることができたのは、プロジェクトメンバー一丸となって取り組んだからこそだと思います。

K.M
そうですね。それぞれの分野でのプロフェッショナルが集まり、真剣に取り組んだ結果がこの高機能なシステムに表れていると思います。プロジェクトを進めるのは大変ではありましたが、私個人としてはずっと楽しかったですね。誰もが前向きに議論したり迅速に対応してくれたりしたため、チームで取り組んでいる感覚が強く、充実した日々を送ることができました。

A.M
「KISSEI Safety LINK」の機能の高さに、私自身とても満足しています。くすり相談センターにいた頃に気になっていた部分は全て反映され、グラフ化も簡単にできるようになりました。情報を絞り込めるソート機能など、前身のシステムにはなかった新機能がいくつも実装されており、非常に使い勝手の良い仕上がりになっています。実際、くすり相談センターのメンバーからも「とても便利で助かっています」という声が届いており、このプロジェクトに携われたことを誇りに思います。

I.T
医薬営業本部やくすり相談センターでは、医療関係者から相談を受けた際に、情報を伝えるだけでなく「KISSEI Safety LINK」の活用方法も説明してくれているそうです。より多くの場面で使っていただけるように、今後もこのシステムを進化させていきたいと考えています。現在考えているのは、「KISSEI Safety LINK」を活用して、医薬品のリスクに関するコミュニケーションの輪を広げていくこと。医療関係者や患者さんの中には、副作用情報に対してマイナスイメージを持つ方もいるかもしれませんが、このシステムを通してリスクとその対策方法などを精細に共有することで不安を払拭し、より良い医療を届けるきっかけにつながるのではないかと考えています。

U.H
I.Tさんが言うとおり、ここで終わりではなくさらにバージョンアップしていきたいですね。「KISSEI Safety LINK」はキッセイ薬品と医療関係者とのリスクコミュニケーションツールですが、その先には患者さんがいます。最終的には、キッセイ薬品、医療関係者、患者さんの三者が柔軟にコミュニケーションを取れるようになることが、製薬企業として目指すべき最終形態ではないかと私は考えています。そのために何ができるか、どうバージョンアップしていくべきか議論していきたいですね。

※社員の所属組織および取材内容は取材時点のものになります。