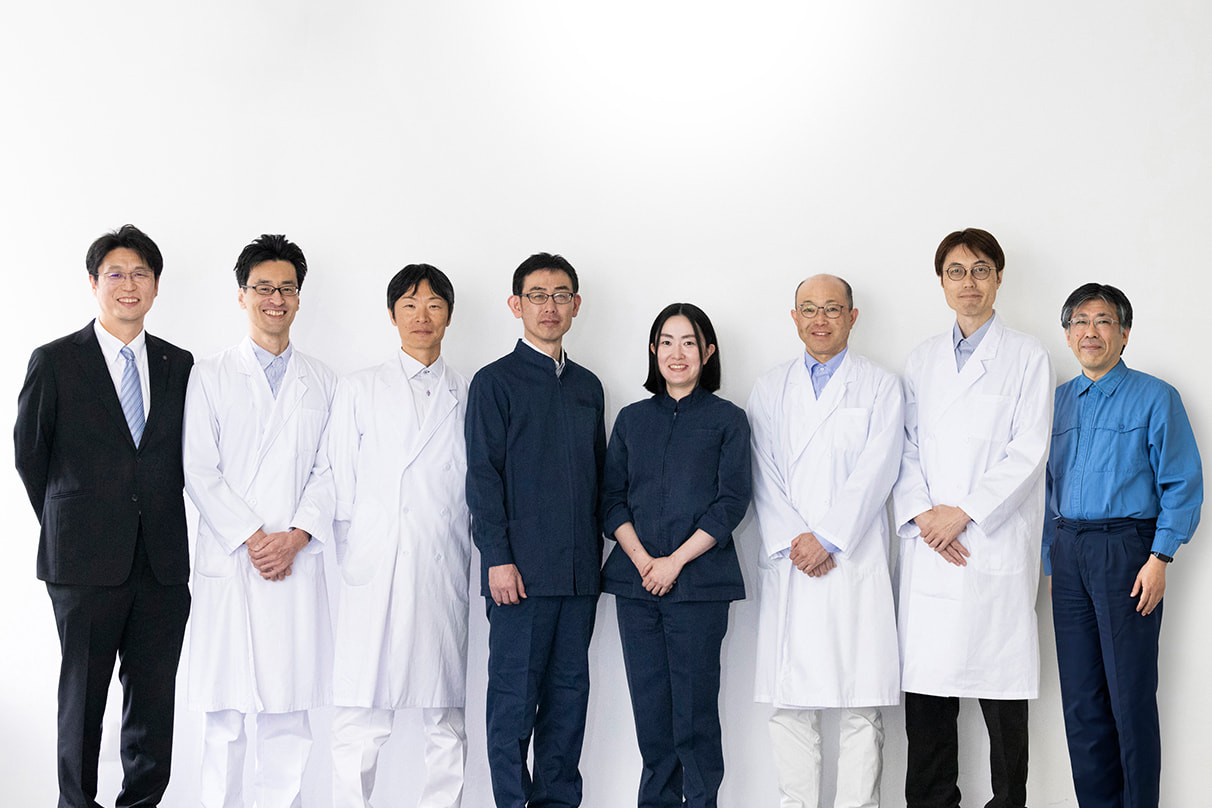プロジェクト
ストーリー
事前にリスクを特定し、
被験者保護とデータの信頼性を保証しつつ
治験の効率化を実現する

臨床試験の規制の変化に適応するべく開始した取り組み。
被験者の保護、治験の品質に影響を及ぼすリスクを事前に特定し、リスクに応じてモニタリングのウエイトを変えることにより、効率性を高めていきます。近年、治験の多様化が進み、EDC(Electronic Data Capture)をはじめとする各種デジタルツールが普及したことにより、治験に関するデータを迅速に収集し、中央で一括管理することが可能となりました。加えて、治験の目的に照らしたデータの重要性や被験者の安全確保の観点で、治験の品質に及ぼす影響を評価し、それらのリスクに応じてモニタリングの工数に幅をもたせる手法が検討されるようになってきました。そこで、臨床試験のオペレーション部門、データマネジメント部門、品質マネジメント部門といったデータ収集に関与する各分野のメンバーが集結。臨床試験のさらなる効率化を目指すプロジェクトを開始しました。
プロジェクトメンバー
左右にスライドしてご確認ください
データの信頼性確保と効率化、
マインドチェンジで両者を実現させる
ープロジェクトの概要を教えてください。

F.N
本プロジェクトは、臨床試験の多様化やデジタル技術の普及に伴い、2018年に始動し、現在も活動が続いています。プロジェクトの目的は、モニタリング業務を含む臨床試験全体の効率化。新薬の研究開発の発展とともに臨床試験方法も多様化し、第一線の業務量も増えていく中で、薬をいち早く患者さんに届けるために臨床試験の効率化はどの製薬会社にとっても急務と言えます。試験を効率化する上でベースにしたのは、「Risk-Based Monitoring(RBM)」と呼ばれる考え方。臨床試験において最も重要なファクターである、「被験者の保護」と「データの信頼性」に影響を及ぼすリスクを試験前に特定し、未然に防ぐように臨床試験のプロセスを構築することで、被験者の安全性を確保しながら、より高品質なデータを取得する新しい考え方です。

S.K
重要度の低いデータの信頼性まで追求してしまうと、データマネジメントだけでなく、第一線のモニタリング業務にも高い負荷がかかります。もちろん、一つひとつの項目を丁寧に確認することで、ちょっとした異変にもすぐに対応できるのは良いことです。しかし、100以上の確認項目がある試験では膨大な時間がかかる上に、複数の試験を受け持つモニターの精神と体力をすり減らしてしまう。そうなると、試験項目の確認に手一杯で、本来、最優先で守られるべき患者さんの保護、重要度の高いデータの信頼性が疎かになる危険性が高まります。だからこそ、全ての項目に同じ熱量を注ぐのではなく、患者さんの安全性に大きく関わるものや、データを評価する上で重要な判断材料になるものに項目を絞る必要がありました。そうすることで、限られた業務時間の中で患者さんの安全性の確保とデータの品質向上に注力できるようになるのです。

Y.M
2018年の始動から現在までを振り返ってみると、これらの取り組みはコロナ禍をきっかけに急速に進みました。医療機関の訪問規制によってモニタリング活動がストップ。モニターが医療機関を訪問できない状況の中、患者さんの安全とデータの品質を守るためには、必要最低限の項目のみを確認するRBMの導入が急務となりました。
ープロジェクトの中での皆さんの役割を教えてください。

F.N
リスクを事前に特定するためには、医療機関ごとに試験状況を把握できる状態にする必要があります。そのため、収集した膨大なデータから重要なものを優先的に見えやすくし、どのフェーズにリスクが発生しているのか誰でも確認できるようにすることが、私たちデータマネジメント担当の仕事です。具体的には、システムの基盤構築やデータの見える化に携わっています。私はデータ収集の観点からRBMの考え方に大いに共感していました。従来のやり方だとあまり重要でないデータも詳細に集められていて、データをまとめる際に非効率さを感じていたんです。そのため、このプロジェクトへの参画が決まった時は、光栄な気持ちでいっぱいでした。

Y.M
私はモニターとして本プロジェクトに参画し、第一線に最も近い視点から効率性の高い臨床試験のプロセス構築に携わっています。試験のプロセス構築に加えて、医療機関と連携を取りながらモニタリングにウエイト付けする新しい手法を第一線に浸透させるのも、私たちモニターの仕事です。

N.T
私も同じモニターとして本プロジェクトに関わることになり、RBMという新しいモニタリング方法の導入に、初期の段階から携われることにうれしさを感じていました。しかし、いざ医療の第一線でRBMを導入しようとすると、スムーズに行かないことも多く、そこは今でも課題に感じているところです。

W.F
私は、コロナ禍にモニターとして本プロジェクトにアサインされました。私の場合、当初は不安でいっぱいでした。医療機関への訪問が制限され、これまでのモニタリング業務ができなくなってしまって、試験を継続できるのかさえわからない状態。それでも患者さんの安全性を最優先に考え、モニタリング手法のブラッシュアップに取り組みました。

M.N
私は入社1年目の時にモニターとしてこのプロジェクトに参画しました。モニタリングの実務経験がまだまだ浅い状態でしたが、新人としてフレッシュな視点から質問したり、意見したりするよう心掛けていました。先輩方も会議のたびに意見を求めてくれて、分からないことがないか聞いてくださったので、早めにプロジェクトの目的や全体像をつかむことができました。

S.K
私は品質マネジメント担当として、F.Nさんのようなデータマネジメント担当の方やモニターの方々と協働しながら、リーダー的な立ち位置でモニタリング手法や品質管理手順の見直しに携わっています。RBMにおいて事前にリスクを予想するためには、専門知識と第一線でのモニタリング経験が非常に重要です。計画した臨床試験が医療機関でどのように行われ、データがどのような手順で収集されるのか、知識と経験に基づいてシミュレーションし、考えられるリスクを全て洗い出すことが求められます。ただ、知識と経験は人によって異なるものだからこそ、メンバー間で個々人の感覚値を共有し、多角的な視点からリスクを考えることも大切にしています。

視点の統一と共通理解を目指し、
部署の垣根を超えて徹底的に話し合う
ー特に難しかったのはどのような点でしたか?

F.N
試験の解析結果や報告書の内容を基に、どの部分を重要データとするか、関連部署全体でコンセンサスを取るのが難しかったですね。データの重要度に対する捉え方が部署によって異なる中で、薬の効能を正確に評価するためにはどのデータを重要とすべきか、全員ですり合わせていきました。

S.K
私もF.Nさん同様、部署間でデータの見方が異なる中で、視座を合わせていくことに苦労しました。ある部署では重要度は低いと捉えているデータでも、他の部署ではそう考えていない場合がある。そんな時は「患者さんにいち早く薬を届ける」という最終的なゴールにみんなで立ち返ることを意識しました。臨床試験においてどの項目が薬の有効性評価に影響するのか、ブレない判断軸を持ち続けることで、それぞれの納得を生みながらモニタリング手法の見直しを進めることができたと思います。

Y.M
一部の医療機関でRBMの考え方をなかなかご理解いただけず、試験の遂行が困難になった時はどうしようかと思いましたね。コロナ禍では、モニターが頻回に医療機関を訪問することができないので、モニターが医療機関で確認しなければならないデータ以外は医療スタッフの方に確認いただくなど、これまで以上に医療機関との連携が重要になります。しかしながら、医療機関はコロナ対応でひっ迫して、それどころではない状態。そんな中、これまで通りのやり方では、治験を効率化できないことも事実。こればかりは何度も話し合いを重ねて、RBMの考え方にご納得いただくほかありませんでした。新薬をいち早く患者さんの元へ届けるためには臨床試験の効率化が必要不可欠であることをご理解いただき、最終的に試験を進めることができました。

W.F
コロナ対応でただでさえ現場が混乱している中で新しい試験方法を導入するのは、医療スタッフの皆さんも不安だったと思います。これまでモニターが医療機関を訪問して確認していた、たくさんの項目が、突然最低限のボリュームになったんですから。そんな不安を少しでも払拭するために、医療機関を訪問しなくてもオンラインできちんとデータを管理できることなど、患者さんの安全性に問題ない旨を丁寧に説明しました。

N.T
あの当時は本当に大変でしたよね。当たり前にできていたことが突然できなくなり、私も戸惑うばかりでした。しかし同時にRBMの重要性を再認識できたのも事実。一つひとつをデータを医療機関で確認できなくなった以上、いち早くRBMに基づいたモニタリング手法を精緻化し、医療機関に浸透させることが私たちの使命だと感じました。

M.N
入社1年目でモニタリング業務の全容を理解するのに精一杯の中、コロナ禍による業務体制の変更が余儀なくされ、頭の中はてんやわんやでした。それでも疑問に思ったことは素直に質問しながら、少しでも早くチームの戦力となれるよう、知識を身に付けていきました。

S.K
どの項目を重要と判断するべきか、未曾有のコロナ禍で正解が見えない議論が続きました。そんな中でM.Nさんから出るフレッシュな疑問のおかげで、試験の本質に立ち返る機会が何度もあったので、今でも感謝しています。


データの可視化が、
新しい発見と経験値の共有を可能にする
ー臨床試験の効率化プロジェクトを通じて、実感した変化や得られた気付きについて教えてください。

Y.M
今回のプロジェクトを経て一番驚いたのは、自分たちの暗黙知が見えるようになったことです。基本的にモニタリングは個人業務のため、過去の経験から医療機関ごとに注意すべき点を各々で把握しているのが通常でした。しかしデータマネジメント担当の皆さんのおかげでモニタリング活動を含むすべてのデータが可視化され、全医療機関での進捗や取得データの異常が一目瞭然に。今までなんとなく把握していたリスクが明確になり、より迅速かつ適切な対応策を打てるようになりました。

F.N
私も医療機関によってデータの品質にバラつきがあることに課題を感じていました。このプロジェクトの中で一番面白かったのは、モニターの皆さんが持つ実感値がぴったり一致していたこと。全医療機関の進捗データを見せた時に「やっぱりここが問題だったんだ!」とデータに対して同じ所感を持っていたのが、とても印象的でしたね。第一線の皆さんの実感値と同じデータが収集できて、さらに自信を持つことができました。

N.T
私も可視化のおかげで、チーム全員が同じ視点で問題を捉えられるようになったと実感しています。プロジェクトに参画した当初、トラブルが起こる前にリスクを想像することができず、先輩方の議論についていくのに一杯一杯でした。しかし、モニタリング活動を含むすべてのデータが可視化され、試験のどの部分にリスクが潜んでいるのか把握しやすくなったんです。おかげで業務経験の浅さを補填しながら、先輩たちと同じ視点でリスクについて話し合うことができるようになりました。

M.N
N.Tさんにもそんな時代があったんですね…!私はこのプロジェクトを通して、それぞれのデータを収集する目的を深く理解することができました。確認項目の優先順位を精査する際、その項目が試験の評価において重要かどうかを、チームで何度も話し合いました。重要かどうか判断するためには、データの収集目的をきちんと理解し、評価にどのように影響するかを考える必要があります。そのため自然とデータの収集目的について考える習慣が身に付きました。この学びを通じて、今後より効率的かつ本質的なモニタリング業務を遂行していきたいです。

W.F
RBMの考え方を採用してから、業務中の精神的な負担が軽くなったように感じています。これまでは全ての項目を丁寧に確認することが当たり前だったため、どれだけ気を使っても見落としがあるのではないかと常に不安でいっぱいでした。しかし、RBMの導入を通じて、各データの収集目的をきちんと理解し、注視すべき項目にメリハリをつけてモニタリングできるようになりました。これからも適切に時間と労力を配分しながら、患者さんの安全確保と高品質なデータ収集に取り組みたいと思います。

新たな技術や考え方をいち早く取り入れ、
臨床試験の効率化を追求し続ける
ー最後に、今後の展望について教えてください。

S.K
臨床試験の効率化が進めば、それだけ多くの新薬が世に出て、患者さんの元へいち早く薬を届けることにつながります。だからこそ、より多くの医療機関に本プロジェクトの考え方をご理解いただきながら、臨床試験の効率化に貢献していきたいです。しかし、業界全体での臨床試験の効率化を実現するためには、私たちの力だけでは不十分。試験の実施先である医療機関や試験の委託業者など、あらゆるステークホルダーとの連携が必要です。コロナ禍でのプロジェクトを経て、医療機関への訪問に頼らなくても、安全性と品質の高い試験が実施できることを証明できたという自負があるので、今後キッセイ薬品が業界のモデルケースとして存在感を高めていけたらと思います。

※社員の所属組織および取材内容は取材時点のものになります。